ライブコマースは、中国やアメリカで急成長を遂げ、今や世界中で注目されている新しい販売手法です。対面販売のようなリアルなやり取りと、eコマースの利便性をあわせ持ち、特に動画に慣れ親しんだZ世代へのアプローチ手段としても有効です。
この記事では、ライブコマースの基本から、日本市場の現状、始め方やおすすめの配信プラットフォームまでわかりやすく解説します。
目次
ライブコマースとは
ライブコマースとは、ライブ配信を通じて消費者とコミュニケーションを取りながら商品を販売する手法です。具体的には、メーカーや代理店がショップ店員やインフルエンサーに依頼してライブ配信を行い、そこで商品の使用方法や魅力を紹介し、視聴者や配信者のファンがその商品を購入する流れとなります。
インスタのフォロワーが一定数以上いると、ストーリーズに購入サイトへのリンクを貼ることができ、視聴者はそのリンクから商品を購入することが可能です。
ライブコマースと従来の通信販売番組との違い

ライブコマースはテレビショッピングに似ていますが、大きな特徴は配信者と視聴者が双方向でコミュニケーションを取れる点です。視聴者がコメント欄に書いた質問に配信者がリアルタイムで答えたり、リクエストに応じて商品の詳細を見せたりできるなど、従来のテレビショッピングにはないユニークな特徴があります。
配信者は、顧客がどんな情報を知りたいのか、どんなニーズをもっているかを直接的に知ることができるため、購買意欲を喚起するためリアルタイムに対応していくことができます。
ライブコマースのメリット

視聴者とコミュニケーションがとれる
ライブコマースの特徴であり最大のメリットは、視聴者とリアルタイムでコミュニケーションがとれることです。質問があれば視聴者はその場でコメント可能で、配信者側はそれに回答することで顧客の疑問や不安を解消することができます。
購入者とのコミュニケーションは、その場での購入につながりやすくなるだけでなく、配信者やブランド・企業そのものの信頼を高めることでブランド構築やブランディング効果にもつながります。
臨場感があり盛り上がりが感じられる
テレビショッピングや録画配信では得られない臨場感は、売り上げや購買体験に大きく影響します。
例えば、果物の生産者が収穫の様子をライブ配信することで、生産者の顔が見えるだけでなく、文字通り採れたての新鮮な果物を購入することができるため、購買体験が高まります。作付けの工夫や今年の出来栄えなど、生産者のリアルな声を直接聞けることも、購買意欲を高めるでしょう。
商品の特徴や魅力を伝えやすい
文章や写真だけの商品紹介よりも、動画のほうが圧倒的に多くの量の情報を伝えることができます。それに加え、ライブコマースでは専門的な知識を持つ配信者が、商品を説明するだけでなく、視聴者から送られる質問にその場で回答したり、リクエストに応えて別のアングルを見せたり動かしてみたりするなど、商品の特徴や魅力を消費者目線でも伝えることができます。
ライブコマースと相性の良いアパレルでは、視聴者のコメントに合わせてその場でコーディネートを組んだり、しゃがむ、回るなどの動きのリクエストに応えたりすることで、実店舗で接客するように丁寧に商品について伝えることができます。また、開封体験をライブで共有することで、商品の質感や使い勝手をよりリアルに伝えることができ、視聴者の購買意欲を高められるでしょう。
ライブ中に商品を紹介し、その場で購入リンクを提供することで、視聴者は衝動的に購入しやすくなります。限定オファーやタイムセールなどの要素を加えることで、さらに購入を促進することができます。
コスパがいい
ライブコマースは、テレビ通販やCM広告に比べて低コストで実施することができます。自社スタッフを配信者として起用したり、機材費を抑えてスマホなどで撮影することで、出費を大幅に抑えることができます。
インフルエンサーを活用できる
ブランドや商品、そのターゲットと親和性の高いインフルエンサーに配信してもらうことで、フォロワーやファンに一気に拡散できるのもライブコマースのメリットのひとつです。
インフルエンサーを起用したSNSマーケティングでも拡散は可能ですが、ライブコマースでは双方向の交流とその場での購入ができるため、インフルエンサーの発信力とファンとの結びつきがより大きな効果を発揮します。
例えば、コスメや美容に精通したインフルエンサーに新作コスメのライブコマース配信を行ってもらうことで、視聴者からの質問に対する専門的な回答や率直な意見、使用アイディアの解説などによって購買につながりやすくなります。
ライブコマースのデメリット

集客が必要
ライブコマースでは集客が不可欠です。視聴者が少ないとリアクションやコメントなどが集まりにくくなってしまいます。
SNSなどを利用した事前の告知やカウントダウンで顧客の関心を高めたり、インフルエンサーの起用などを行ったりして集客するようにしましょう。また、新商品発売時には必ずライブ配信を行うなど、スケジュール化して顧客に認識してもらうことで視聴者を集めやすくするのも良いでしょう。
配信時間が限られる
録画配信と違いリアルタイムで配信するライブコマースは、配信時間が限られるのがデメリットのひとつです。ターゲット視聴者がもっとも多く集まる時間に配信を行うことが大切になるため、必然的に夜や休日など顧客が自由に視聴できる時間帯が配信時間になります。通常の就労時間以外に配信を行うことになる可能性もあり、労働時間や人の確保が必要になります。
配信者の力量や配信内容に左右される
ライブコマースは発信力とコミュニケーションが成功の鍵であるため、配信者の力量によっては商品の魅力が伝わらないばかりか、視聴者の誤解を招いたりネガティブなイメージを持たれたりしてしまいます。ただおしゃべりが上手ければ良いわけではなく、商品に対する知識、視聴者に対する誠実さを持つ配信者が必要となります。
配信環境や配信者の口調やトーンがブランドの世界観と大きくかけ離れた雰囲気であったり、視聴者の感覚とずれていたりすることも、イメージ低下につながってしまいます。例えばハイブランドのルイ・ヴィトンは、中国をターゲットに行った初めてのライブコマースで、ブランドの世界観に合わないチープな配信環境が視聴者の不評を買い、ブランドイメージを低下させてしまいました。
コンテンツが使い捨てである
ライブ配信は広告や商品紹介動画のように繰り返し配信されたり固定して表示されたりするものではなく、基本的にはその場限りのものになります。配信中の売り上げがあがらないと、配信にかけた時間や労力などの費用対効果が低くなってしまいます。
良質な配信を行ってアーカイブとして残すことで、リアルタイム視聴できなかった顧客に見てもらうことができます。また、配信中のコミュニケーションで顧客のエンゲージメントやロイヤリティを高め、次回の配信や他の販売チャネルでの購買につなげてコンテンツの費用対効果をできるだけ高めると良いでしょう。
日本のライブコマース市場

日本のライブコマース市場は認知度が低く、大きな市場を持つ中国や成長の兆しが見えるアメリカと異なり伸び悩みが見受けられます。2023年のNTTコム リサーチの調査によると、ライブコマースを知っている人の割合は31.9%、視聴したことがある人は3.9%でした。その後も爆発的に普及したとは言えませんが、SNSを通じて購入するソーシャルコマースが広まりつつあることからも、新たな市場として拡大する余地は充分にあるでしょう。
さらに、アメリカや中国で社会現象にもなっている「TikTok Shop(ティックトックショップ)」が、2025年6月から日本でもサービスを開始することは大きな転機となる可能性があります。Z世代に人気があるTikTokの参入をきっかけに、ライブコマースが一段と加速する可能性も高いでしょう。
ライブコマースの日本での成功事例
まだ発展途上の日本でのライブコマースですが、いくつかの企業やブランドはライブコマース配信を行い顧客のエンゲージメントやロイヤリティ、売り上げを獲得して成功しています。
資生堂のライブコマース
化粧品メーカーである資生堂は2020年に日本でのライブコマースを開始しました。配信者は資生堂のメイクアップアーティストや開発者で、視聴者からの質問などに専門的な知識を交えて回答してくれるため、より深く商品について理解することができます。
また、タレントやお笑い芸人などを起用したライブ配信イベントや、ライブ配信視聴特典としてのクーポン配布で視聴者の獲得と購入へつなげる工夫も行っています。
ライブコマースは自社サイトから配信されますが、インスタライブと同時配信することでより多くの顧客やターゲットへリーチできるようにしています。
UNIQLO(ユニクロ)のライブコマース
アパレルメーカーのUNIQLOもライブコマースを活用しています。ユニクロはLIVE STATIONと呼ばれる自社サイトから定期的に配信していて、店舗スタッフが配信者となり、商品の紹介を行っています。
配信の最初にライブコマースの使い方の説明をする、着用者の身長や骨格タイプを伝えるなど、初めての視聴者でもコメントやリアクション、購買がしやすい環境を作る工夫がされています。
画面上に映る配信者とは別に司会役もいることで、商品紹介とコメントのピックアップの役割分担がなされ、視聴者のリクエストや質問にスムーズに対応できるようになっています。

ニトリのライブコマース
インテリア用品店のニトリでは、ニトリLIVEと呼ばれるライブ配信を行っています。店舗内で配信が行われ、その場で視聴者にテーマに沿ったアンケートをとってピックアップするアイテムを決めるなど、ライブコマースの特徴である双方向コミュニケーションを最大限活用しています。
また、紹介したアイテムの中で気になったものをストックできる機能があるため、ライブ配信後に落ち着いて気になったアイテムをチェックすることもできます。
ニトリLIVEの公式サイトでは配信スケジュールをカレンダー表示して見たいテーマの配信日が一目でわかるようになっており、視聴者を獲得する工夫がされています。
中国のライブコマース市場

ライブコマースは2016年5月に中国企業Alibaba(アリババ)社がTaobao Live(タオバオライブ)をスタートしたことで大きく注目を浴びました。中国での大きなセールである11月11日の光棍節(こうこんせつ)、通称「独身の日」のセールで新ツールとして導入された背景があります。中国・米国のライブコマース市場規模の記事によると、2017年の中国のライブコマース市場規模は約392億円ほどでしたが、2023年に98兆円にまで急拡大しています。
ライブコマースが定着し人口も多い中国のライブコマース市場は、日本の企業にとっても越境ECの大きなチャンスの場となると考えられます。実際に、コクヨ中国や山梨県観光振興課などの日本企業や団体が中国向けのライブコマースを展開し、多くの売り上げや宿泊予約などにつなげています。
日本では中国のようにライブコマースが流行らない理由
中国でライブコマースが急速に定着した背景には、「ライバー(ライブ配信者)」と呼ばれるインフルエンサーの影響力が大きく関係しています。KOL(Key Opinion Leader)と呼ばれる彼らは高い信頼を得ており、「憧れのインフルエンサーと同じ商品を使いたい」という視聴者の心理が購買行動を後押ししています。さらに、販売力を持つライバーがメーカーと価格交渉を行うことで、ライブコマースで購入するほうが安く購入できるなど、他の販売チャネルとの差別化もできています。
一方日本には、爆発的な人気や信頼を得ているライバーがほとんどいないことに加え、商品物流が確立しているためライブコマースや一配信者に特別な価格を提供できる環境がありません。また、悪質なコメントのコントロールができないなどネガティブな要素も加わり、ライブコマースをはじめる利点が少なくなってしまったのも日本で流行らなかった要因でしょう。
アメリカのライブコマース市場

アメリカのライブコマース市場は2023年末に売上高550億ドルを記録し、2026年までにはライブコマースがアメリカ国内の販売の5%を占めるだろうと予測されています。
2020年頃まではウォルマートがクリスマスセールなどの大規模セールで実験的にライブコマースを実施しているだけでしたが、その後専用サイトが立ち上げられ、現在では日々多くの配信が行われています。
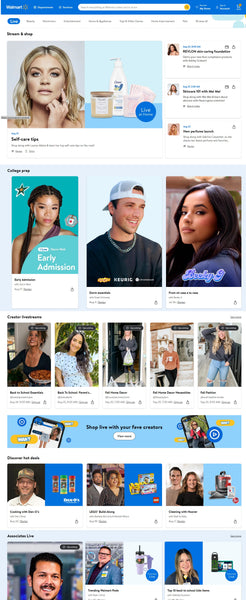
Amazon Live(アマゾンライブ)などのプラットフォームも展開されており、三菱自動車が新車発表イベントを行って成功を収めています。
日本のライブコマースプラットフォーム
- Tig LIVE(ティグライブ):配信者が商品バーコードを読み取るだけで画面上から購入できるようになるなど、、ライブ配信に適した機能を備えています。また、Shopify(ショッピファイ)のECサイトと簡単に連携することができます。
- Live kit(ライブキット):自社ドメインでライブコマースを展開するためのツールに加えて、運用していくためのコンサルティングやサポートもワンストップで提供しています。
- 楽天市場ショッピングチャンネル:国内最大級のオンラインショッピングモール、楽天市場が運営しているプラットフォームです。各店舗が独自に配信する「スポット配信」のほか、楽天市場のキャンペーンに合わせた日程で配信する「イベント連動配信」を行うことができます。
- Sharing Live(シェアリングライブ):産直品に特化したライブコマースプラットフォームです。生産者自ら商品を紹介できるライブ配信は、農業・漁業・伝統工芸などと親和性が高く、自治体の町おこしなどにも活用されています。また、出店料や固定費は不要で、販売手数料のみで利用できる点も特徴です。
- Peace you LIVE(ピースユーライブ):年間100万点以上の販売数を誇る、モール型のライブコマースアプリです。固定費はかからず配信時間や販売額に応じた手数料で利用できます。また、Peace you LIVEに在籍するライバーに依頼して、店舗から配信してもらうこともできます。
- HandsUP(ハンズアップ):日本最大級のライブ配信アプリ17LIVE(イチナナ)が提供するライブコマースソリューションです。配信用ツールのほか、コンサルティングなども利用できます。
これらのプラットフォームを利用する以外にも、インスタグラムやYouTubeなどのライブ配信とECサイトを併用することで、ライブコマースを行う企業やブランドも多くあります。
ライブコマースのやり方

1. 配信するプラットフォームを選ぶ
すでに固定ファンがいる場合や集客が見込める場合は、Tig LiveやLive Kitのように自社サイトなどに配信機能を埋め込めるプラットフォームがおすすめです。配信の自由度が高く、ECサイトと連携することで視聴者がその場で購入することができます。
視聴者を集めるところから始める場合は、SNSや利用者の多いプラットフォームを選びましょう。インスタライブやTikTokなどを配信先とすることで、多くのユーザーを視聴者として獲得できます。その場合はECサイトへ誘導できるよう、プロフィールにリンクを貼っておくなどすると良いでしょう。
2. 配信環境を整える
まずは安定した通信回線を確保し、スマートフォンやカメラ、マイク、照明などもなるべく撮影に適したものを用意します。配信者も身だしなみをしっかり整え、顔色が明るく見える色の服を着るなど、視聴者に好印象を与えるように準備します。
また、商品をわかりやすく説明するには事前の練習が必要です。サイズ感を伝える際などは「縦〇cm、横〇cm」と説明するよりも、500mlのペットボトルを横に並べる、横に立って見せるなど、動画配信の利点を活かして、視聴者がイメージしやすい工夫をすると良いでしょう。
3. 視聴者を集める
配信日時や視聴方法は、InstagramやX、LINEなどのSNSを活用して予告しましょう。数日前から複数回告知を行い、当日も「本日〇時から配信開始!」とリマインドすることで、参加率が上がります。
特にターゲットに合わせたハッシュタグや画像付き投稿は、目に留まりやすく効果的です。また、配信内容の一部を事前に紹介することで、興味を引きやすくなります。
4. 配信後の分析を行う
配信準備、配信内容、売り上げた結果など、必要に応じて振り返りや分析をすることで次回以降の配信に活かすことができます。特にライブコマースをはじめたばかりの段階では、アーカイブや配信の録画を見返して、音声や画像、照明の具合、配信内容にわかりにくい部分がなかったかなどを視聴者目線でチェックします。
まとめ
日本のライブコマース市場は、まだ発展途上ではあるものの、Z世代を中心とした動画世代の台頭により、今後大きな成長が見込まれます。
ライブコマースは配信者と視聴者がリアルタイムで交流できる双方向性や、コストパフォーマンスの高さなど、多くのメリットがあります。成功事例も徐々に増えており、今こそ新たな販路拡大の手段として取り入れる絶好のタイミングと言えるでしょう。
続きを読む
- 【速報】2022年度IT導入補助金が申請受付開始!
- D2Cとは?成功させるポイントと、ブランド事例11選から極意を学ぶ
- 総額表示への移行の準備を始めましょう
- BNPLとは? 後払い決済を導入したいショップ運営者にそのメリット・デメリットを解説!
- Amazonアフィリエイトでネット販売を拡大する方法
- ギグエコノミーとは。市場規模、将来の成長予測、今後の働き方
- POSシステムって何? POSソフトウェア&ハードウェアを徹底解説
- ネットショップ開業におすすめのサイト20個紹介! メリット・デメリットや注意点は?
- Shopifyに新機能追加 マーケティングセクションでGoogleとFacebook広告を管理しよう
- 絵文字SEO:検索順位上昇のために絵文字を使うべき11の理由
よくある質問
ライブコマースとテレビの通販番組はどのように違う?
従来のテレビ通販は、一方的に情報を伝える「受け身型」でしたが、ライブコマースは視聴者との双方向コミュニケーションが特徴です。コメントや質問、リアクションをリアルタイムで送れるため、配信者も視聴者の反応に合わせて柔軟に対応できます。
このやりとりが信頼感や購買意欲を高める、大きな強みとなっています。
インスタライブとライブコマースの違いは?
インスタライブとライブコマースの違いは、EC機能がついているかどうかです。
インスタライブでは直接商品を購入する機能はなく、ショッピングページやECサイトへ誘導する必要があります。一方、ライブコマースの専用プラットフォームではライブ配信とEC機能が一体となっているため、視聴中に画面に表示される商品アイコンなどをタップして、購入ページへと進むことができます。
文:Takumi Kitajima







